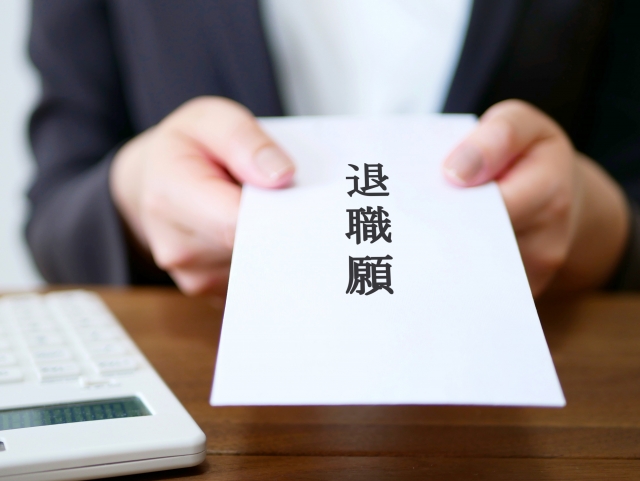私は会社を辞めた後、3年間だけ品質管理のコンサルタントをやっていました。
プロフィールにも書いた通り、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「新現役パートナー」に工場の検査ライン診断・アドバイザーとして登録、3年間活動したのです。(現在ではこの取り組みは廃止になっています)
全くの無名なエンジニアだった私が、どうやって品質管理のコンサルタントになれたのか。
そして仕事のオファーはあったのに、どうして3年でコンサルタントを辞めてしまったのか。
それをお話したいと思います。
これから品質管理のコンサルタントとして独立を目指す人には参考になるはずです。
ぜひ最後までお読みください。
私が品質コンサルタントになれた理由とは?
私の本業は機械設計、生産技術、設備保全といった職種です。
事務機メーカーと半導体工場で合計30年ほどエンジニアをやっていました。
同時に半導体工場で、ある検査工程の品質管理全般にかかわっていました。きっかけはその工程に検査設備を導入したことです。
その工程とは、ひと言で言えば半導体部品、電子部品、精密部品の微細な外観品質を検査する工程でした。
私は気が付けばその工程に20年関わり続け、自分でも知らないうちにその分野の専門家になっていました。
そして私は蓄積した検査ノウハウを会社のホームページに公開したり、特定の顧客にメールマガジンの形で発信していました。
記事は気楽に読めるコラム形式で、専門的なノウハウを分かりやすく、面白く読めるように書き続けました。
これが予想外に好評で、いくつかのセミナー企画会社や出版社の目に止まり、セミナー講師や書籍執筆(共著)の依頼がくるようになったのです。
私としては全くの想定外、驚きのオファーでした。
在職中にこうした活動をやっていたおかげで、退職後も継続してセミナー講師や書籍出版の依頼がきました。
そして前にも書いた通り、退職後に独立行政法人中小企業基盤整備機構の「新現役パートナー」に工場の検査ライン診断・アドバイザーとして登録しました。
その肩書のおかげで、コンサルタント業務の依頼も頂きました。
この枠組みでは対象企業は中小企業に限定されていたのですが、私のセミナーに参加して頂いた企業からもコンサルタント業務の依頼を頂くようになりました。
こちらは大企業からの依頼もあり、件数は多くないものの貴重な体験をすることができました。
こうして私は退職後に品質管理コンサルタントとして活動をやることになったのです。
私がコンサルタントになれた理由をまとめると、こうなります。
・
②ニッチな分野ゆえに専門家の数がそう多くなく、無名だが実績のある私に仕事の声がかかった。
・
③「新現役パートナー」の肩書が信頼を生んで仕事の依頼が来た。
・
④在職中に会社のホームページやメールマガジンで事前の営業活動が出来ていた。
やはり個人で仕事を受注するには他にない強味、顧客にとってのメリットがないと難しいです。
希少価値が必要なのです。
私がコンサルタントを辞めた理由とは?
私が曲りなりにも3年間とは言え品質コンサルタントがやれたのは、20年近い現場経験があったからです。
日本国内の工場だけでなく、海外の工場でも多くの経験を積んできました。
本屋に並んでいる品質管理のマニュアルには絶対出て来ない、現場の問題解決事例を沢山経験していたのです。
セミナー講師をやっていると一部上場の大企業からも品質管理や製造部門の品質担当者などが受講されました。
そしてセミナーでどんな質問を受けても回答に困ることはありませんでした。
そうした大企業の第一線の品質管理担当者を相手に自分の経験してきた知識やノウハウを話すのですが、これが自分でも意外なほどに好評でした。
それでセミナーを開催していた会社から何度もリピートのオファーが来たのです。それも複数の会社から頂きました。
机上の論理ではない、活きた現場のノウハウを語ることがセミナー好評の最大の理由でした。
ただし、どんなコンサルタントでも同じでしょうが、長年続けていくことは非常に難しいです。
何が難しいかと言えば、新しい知識、情報、ノウハウを取り込むことです。
会社を辞めてしまうと現場からも離れてしまいます。
するとコンサルタントとしての品質を維持するだけの知識、情報、ノウハウが入手出来なくなります。
客先の現場には入りますが、私の場合は必要な量や鮮度を確保出来ませんでした。
自分の持っている知識やノウハウがどんどん陳腐化していきます。それゆえ私は3年間でコンサルタントを辞めたのです。
もうこれ以上は無理だと悟りました。
これが私がコンサルタントを辞めた理由です。
現場を離れたコンサルタントなど何の役にも立ちません。いかに多くの現場を知り尽くしているか、そこがコンサルタントの生命線だと思います。
品質コンサルタントになるのに資格は要らない!
品質管理コンサルタントに限りませんが、何かのコンサルタントを名乗るのに特別な学歴や資格は必要ありません。
私自身、普通の国立の4年制大学の工学部卒であり、コンサルタントに関する資格など持っていません。
むろん、コンサルタントの中には資格を持っていないと事実上仕事が出来ない場合もあります。
例えば、法律の相談には「弁護士」、税の相談には「税理士」の資格が必要となります。
これらは法的な規制があるので必須条件となります。
あるいは財務や経営のコンサルタントをやるには「公認会計士」、「税理士」、「中小企業診断士」などの資格は必須です。
あるいは「MBA」を取得していることも経営学の専門家であることの証明になります。
その点、品質管理のコンサルタントは特に必要な資格はなく、顧客に問題解決能力があることを信用してもらえればそれでビジネスとして成立します。
それには何よりもまず実績でしょう。コンサルタントとして過去にどれだけ顧客の問題解決に成功してきたか、それが信用される根拠となります。
私の場合も20年近くに渡って数々の大手半導体メーカーや電子部品メーカーを相手に1つの分野をずっと担当していたので、気が付けば膨大な量のノウハウの蓄積があった訳です。
それを私なりに体系化し、セミナーのテキストにしたり書籍として執筆した訳です。
だから私としては単に自分の仕事の履歴をまとめただけとも言えます。
あなたが品質コンサルタントになるためには?
コンサルタントになる一番オーソドックスな方法は、各種コンサルタント派遣を請け負う法人や企業に就職することです。
そこから更に自営業として独立する道もあります。
大手の転職エージェントサービスではコンサルタント業界の求人も用意しています。
ただ、コンサルタント業界全体の求人数はとても多いのですが、品質管理専門となるとかなり減ります。
リクルートエージェント、doda、リクルートダイレクトスカウトの例を紹介しましょう。
【品質管理コンサルタントの求人件数】
| 転職エージェント | 求人件数 |
| リクルートエージェント | 583件 |
| doda | 555件 |
| リクルートダイレクトスカウト | 907件 |
*2022年9月求人検索による調査結果。この他に非公開案件あり。時期によって件数は変動します。
このように件数は少ないのですが、予定年収は高額です。
平均で600万円以上、800万円~1,500万円クラスの求人も普通に見つかります。
ただし、仕事内容を見ると当然ですが非常に高度な専門知識、スキルを要求されます。
求人は半導体、自動車、IT業界、食品業界、それにISOなどの認証団体など多岐に及びます。
そして品質管理の問題解決には、経営や人事に関する知識を必要とする場合が多く、専門外であっても勉強しておく必要があります。
リクルートエージェント
求人件数が国内最大級の転職エージェント
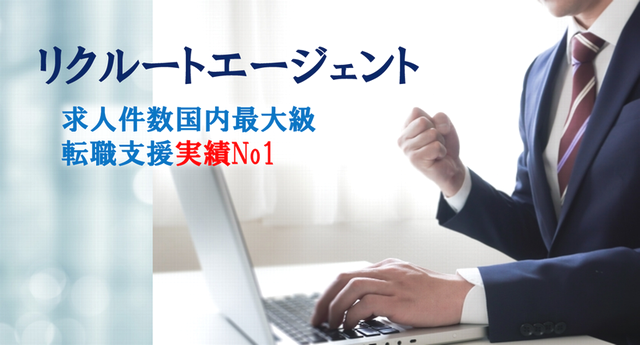
■品質管理の求人件数は国内最大級。希望条件で求人が見つからない場合はぜひ登録してください。
| 項 目 | 概 要 |
| サービスの特徴 | 求人件数は国内最大級。品質管理の求人も最大級 |
| 品質管理コンサルの求人 | 9,700件以上 |
| 求人が多い業界 | IT・化学・産業機械・自動車・半導体・食品など |
| 強みを発揮するエリア | 全国 |
| 未経験者の応募 | 全体の求人件数が多いので、他のサービスよりは探しやすい |
| 主な対象年齢 | 求人が多いので全年代で利用可能 |
| その他 | 転職支援実績ナンバーワン |
| 注意点 | 品質管理の求人は50%以上が非公開。登録して情報入手。 |
【リクルートエージェント】
※リクルートエージェントのプロモーションを含みます。
doda(デューダ)
迷ったらまず登録、転職活動の鉄板転職エージェント

■求人件数が多く、しかも情報が丁寧で詳しい。まずは自分である程度探してからエージェントに相談したい人におすすめ。
| 項 目 | 概 要 |
| サービスの特徴 | 求人情報が詳細で分かりやすく、転職者満足度No1サービス |
| 品質管理の求人 | 2,500件以上 |
| 求人が多い業界 | 産業機械・半導体・自動車・化学・素材など |
| 強みを発揮するエリア | 全国 |
| 未経験者の応募 | 全体の求人件数が多いので、他のサービスよりは探しやすい |
| 主な対象年齢 | 求人が多いので全年代で利用可能 |
| その他 | スカウトサービス、パートナーエージェントサービスも利用可 |
| 注意点 | 非公開案件に好条件の求人あり。登録して情報入手 |
【doda(デューダ)】
リクルートダイレクトスカウト
年収アップ、ハイクラス転職をめざす転職エージェント

■コンサルタント業界、建設業界など他の転職エージェントには少ないジャンルに高額年収の求人を揃えています。
| 項 目 | 概 要 |
| サービスの特徴 | ハイクラス限定のヘッドハンティングサービス |
| 品質管理の求人 | 8,200件以上 |
| 求人が多い業界 | IT・コンサルタント・建設・メディカル・メーカーなど |
| 強みを発揮するエリア | 主に関東、関西、東海 |
| 未経験者の応募 | 未経験者不可(異業種、異職種の転職はあり) |
| 主な対象年齢 | 20代からシニア世代まで、能力があれば応募可能 |
| その他 | 専門的なスキル、キャリアのない人には不向きなサービス |
| 注意点 | プロフィールが求人条件に合わない場合は紹介されないこともあり |
【リクルートダイレクトスカウト】
※リクルートダイレクトスカウトのプロモーションを含みます。
まとめ
以前、『品質管理・品質保証の転職 250人の疑問・不安・悩み』と言う記事を載せました。
その時調べた250人の質問の中に、
「品質コンサルタントとして独立するためには何が必要ですか?」
と言うのがありました。
通常の品質管理に関する知識の量が多くて、スキルが秀でていてもそれだけでは品質コンサルタントにはなれません。
顧客企業にしてみたら、わざわざ外部にコンサルタントを依頼するメリット、理由は何でしょうか?
それは社内では絶対にカバー出来ない問題抽出力、問題解決力を得ることが出来るからです。それをコンサルタントが提供してくれるからです。
法人や企業に属したコンサルタントにしろ独立したコンサルタントにしろ、あなただけの付加価値、市場価値が必要です。
あなたにしか解決出来ない専門分野で勝負すること、これが品質コンサルタントとして成功するための条件です。